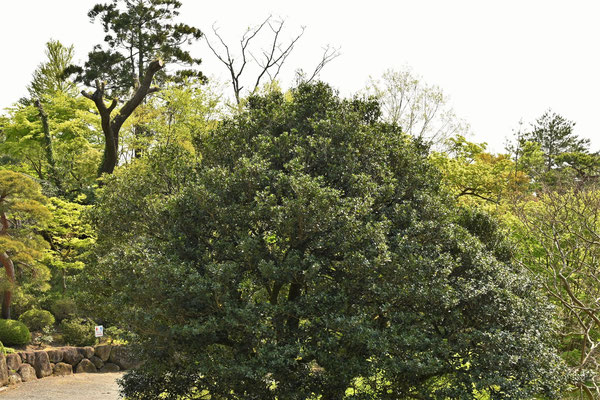縁起の良い木 - 庭木図鑑 植木ペディア
庭木図鑑 植木ペディア > 縁起の良い木
縁起の良い木
木の種類が多すぎて何を植えたらよい迷ってしまうという方は、いっそのこと縁起がいいとされる木を植えてはいかがでしょうか。
植物の縁起に係る俗説は玉石混交で、非科学的であることも確かですが、古くから栄える屋敷の庭に、邪気を払うとされる木や魔除けの木が多いのも事実です。樹木選びに迷ったら俗説に身を任せるのも一つの方法ではないでしょうか。
ここでは代表的な縁起の良い木をピックアップしています。各樹木の詳細については樹木名をクリックして各ページを御覧ください。
蛇足ですが、いずれもの木も人生の吉凶を保証するものではなく、いにしえの人が遊び心で話題作りのために言い伝えた、と管理人は理解しています。
マツ(松)
過酷な環境に耐え、一年を通じて緑の葉を保つマツは古くから神聖視され、門松などの正月飾りにも使われてきました。いろいろなマツがありますが代表的な品種は以下の3つです。
タケ(竹)
管理が難しいことは確かですが、適切な場所で健全に育てれば縁起がよいとされ、タケノコによって旬を味わうこともできます。画像はクロチクですが数多くの品種があります。
ウメ(梅)
ユズリハ(譲り葉)
ダイダイ(橙)
キンカン(金柑)
オリーブ(橄欖)
聖書にもその名が登場するオリーブには「平和」や「勝利」といった花言葉があり、庭に植えると邪気を払うとされます。剪定しにくいのが難点ですが、風水などの影響もあってシンボルツリーに利用する例が増えています。
ゲッケイジュ(月桂樹)
ヒイラギ(柊)
モチノキ(黐)
クロガネモチ(鐵黐)
モチノキの近縁で同じように語呂合わせですが、こちらはさらに分かりやすく、「苦労なく金持ちに」との願いを込めて縁起木とされます。赤い実がたわわに稔り、鳥の活動によって自然に生えることも稀ではありません。
ギンバイカ(銀梅花)
ナンテン(南天)
「縁起の良い木」として真っ先に思い浮かぶのはコレという方も多いのでは。たわわに稔る赤い実は鳥を呼び、知らぬ間に増殖することも。最近では管理が容易なオタフクナンテンが大人気です。
ヤツデ(八手)
大きな葉を「手招き」に擬え、飲食店の店先に植えて客を招くという商売繁盛の木です。名前を知らなくても実物を見れば「あぁこれか」と思う方が多いでしょう。日陰に強く、路地裏でも植栽できます。
マンリョウ(万両)
センリョウ(千両)
縁起の良い下草
「縁起の良い木」のページですが以下は「木」ではなく「草」です。いずれも多年草ですので一度植えれば長く楽しめます。また日陰を好むため、薄暗くなりがちな大木の下で野趣に富んだ景色を作ることができます。
 庭木図鑑
植木ペディア
庭木図鑑
植木ペディア